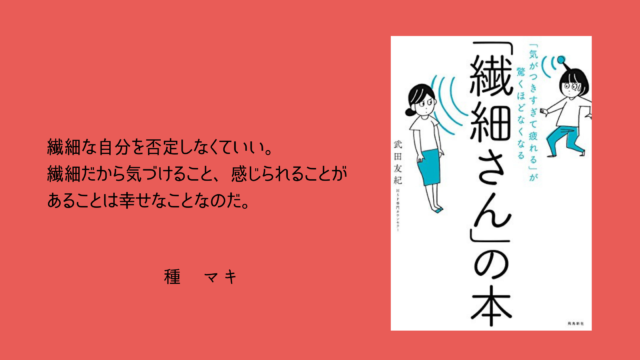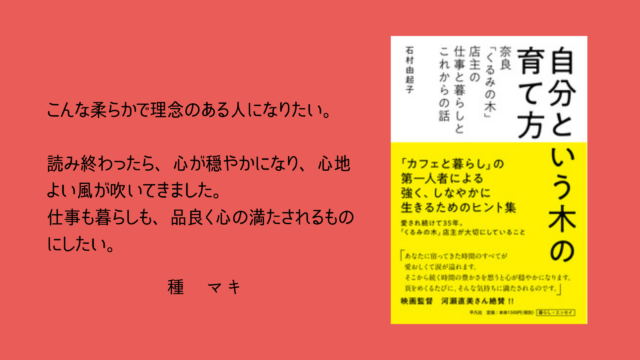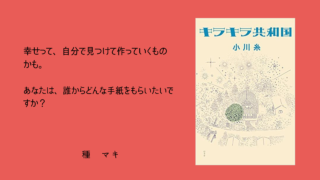「母性」という言葉で何をイメージしますか?
広辞苑では、「母性」を調べると、母として持つ性質。また、母たるもの。と記載されています。
でも、正直、母としての性質、母たるものって何?という感じでイメージしづらい。
「母性」という言葉に苦しんでいる人も多いと聞きます。
「母性神話」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう?
誰かが言う「母性」「母親らしく」の言葉がプレッシャーだったり、しっくりこない感じがすることって、多いと思います。
LGBT的な男女の話や旧来の男女の役割イメージは置いといて(これも、本当に大切なことだけれど)、女性も「男性的」「父性的」な関わりが必要な場面、男性の中でも「母性的」な面が強い人もいるので、「母性」という言葉が、必ずしも「母」「女性」の言葉ではないと思うのだけれど。
と書いている私の頭も「母性」という言葉を、どう捉えるのがいいのか、自分自身母になってもうずいぶん長いのに、わかりません。
多様性の時代だから、その人、その人が自由に思えばいいんじゃない?とも思うけれど、「他の人からどう見られるか」、「他者からの期待」もあるから難しい。期待なんて生やさしいものじゃなくて、「価値観の押しつけ」もあるから、「母たるもの」って難しい。
いきなり、抽象的で毒のある言い方になってしまったのだけれど、それだけ「母性」って言葉は、一筋縄ではいかない言葉なんだと思います。
「母性」という言葉には包み込むような感じと、使われ方によっては不快感もある両面性があります。本を買うときには意識していなかったのですが、『母性』という両極端なイメージの言葉を、著者の港かなえさんだったら、どうダークな小説にされるのかと無意識な期待があったのだと思います。
著者 港かなえさんはイヤミスの女王
「イヤミス」初めて聞かれた方もいらっしゃいますよね?
私も最近まで知りませんでした。
「イヤミス」とは「読後、イヤな気持ちになるミステリー」のこと。
この『母性』を読んでいるときにもイヤな感じ、気持ち悪さを感じました。気持ち悪くて、途中2日間読まずにいました。というものの続きが気になるので、読まずにはいられずその後は一気読み。
今回のレビューする『母性』の前に、港かなえさんの他の作品も紹介します。
港かなえさんの作品の中でも、特に有名なのが『告白』。
小説を読んだことのない人でも、映画『告白』で知っている人もいるのではないでしょうか?
主役の松たか子さんがシングルマザーの教師役で、かなり話題になった映画でしたね。
このダークさ、後味の嫌な感じが「イヤミス」なのです。
『告白』は港かなえさんのデビュー作。
2008年度週刊文春ミステリーベスト10 第1位、2008年度このミステリーがすごい! 第4位
2009年度本屋大賞受賞。そして現在も重版され続けている本です。
その後も『贖罪』『望郷』『Nのために』『夜行観覧車』『リバース』『ユートピア』『ブロードキャスト』『ドキュメント』など次々と作品を発表。
映画化、テレビドラマ化、漫画化された作品も多数という超売れっ子作家さんです。
『母性』の話の進み方について
「母の手記」「娘の手記」「母性について」で構成されており、章の中でも語り手が変わりながら、話が展開していきます。
何度も母性とは?と問いかけられているように感じました。
そして語り手によって見え方、つまり語り手にとっての事実と他者からみた事実や思いの差、気持ちのすれ違いに圧倒されました。
語り手は「私」「わたし」と表現していますが、このレビューでは、わかりやすくするために、「祖母」「母」「娘」と書くことにします。
わかりにくいけれど、あえて名前で書かないのには意味があります。
小説の中でも名前が出てこないのです。
自分の見方と他者からの見え方、感じ方は違うことが多いこと、そして大抵その視点を私(このレビューの書き手)は、忘れてしまうことに気がつきました。
小説の中で、それぞれの出来事の繋がってくる後半のスピード感は圧巻です。
『母性』の違和感や気持ち悪さ
母と祖母の関係に違和感を感じました。自分の全てを受け入れ褒めてくれる祖母。褒められることを期待する母。自分の娘にも、祖母に褒められる行動を要求する母に、正直、気持ち悪いと思いました。
どうして、そこまで認めてほしいんだろう? 小説の中には直接は書かれていないのですが、2人の関係がそうなった経緯を知りたくなるほどでした。
読者が自分の母親とどんな関係であったか、母親とどんな会話をしてきていたかにもよると思うのですが、「こんな会話、褒め方はありえない!」と、鳥肌が立つような、気持ち悪さを祖母に感じました。下手な芝居のようにわざとらしく、それを喜んでいる母にも共感できませんでした。
小説を読んでいて母についての気持ち悪さは、この気持ち悪さは母子関係の中で際立っています。つまり、母の娘としての部分、母親である部分で強く感じていました。夫婦関係や夫の両親、夫の姉、妹の関係の中では、あまり目立ちません。それでも、こんなときに「自分の母はどう言うだろうか」というフィルターは常にかかっています。
意地の悪い姑も息子の母ですね。
母と娘の関係について
私(このレビューの書き手)は、母のことを好きになれない。白々しい感じがすることと、いつまでも親からの愛を求め、娘に対して母らしさが欠けているからだ。
娘は聡明な子で、嫌な感じはしない。母の愛情を強く求めていながら表現できない面はあるものの、そんなに変な育て方はされていなかったのではないかというのが、最初、本を読んだときの感想でした。
しかし、後半部分を読み直してみると、聡明でいつも母の味方になるような女の子であるというのは、母の愛情を強く求めていたからではないか。「いい子」であれば、母に愛してもらえると思い、無意識でそうなっていたのではないかと感じました。
読み直すことで娘の印象が変わったので、再読したら、母がそうならざるをえなかったことに、共感できる部分が出てくるかもしれません。1回目の読書では気づけなかった部分を感じたくなってきました。
私自身のこと 母との関係について
自分(このレビューの書き手)が母になって、自分の子育てに母親の影響がここまで大きいものとは思っていませんでした。母のやり方で嫌なことがいろいろあり、それを反面教師として子育てしてきました。子育てすることは、自分はどう育って、何が嫌だったのか振り返ることでもあリました。
子育ての苦しさは、子どもに手がかかることだけではないんですね。
そんな自分にとって、母子一体感が非常に強い「母」と「祖母」の会話を聞いていると非常に気持ち悪い。娘としての母の、祖母へのベタベタした感じが、特に嫌な感じと受け取ってしまうのです。
この本での母性について
終章「愛の歌」は全て 母性について である。語り手が
……と思う気持ちが、母性なのではないだろうか。
『母性』 終章より
と言っている。実際には……の前に文章があるのだけれど、これをレビューの中では書けない。
小説全体を読んで、そのうえでここに辿り着いてほしいと思うからだ。
『母性』本のデータ
- 著者 港かなえ
- 出版社 : 新潮社
- 発売日 : 2012/10/1
- 単行本 : 266ページ